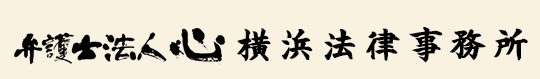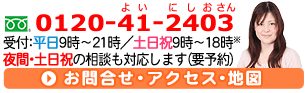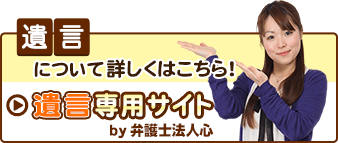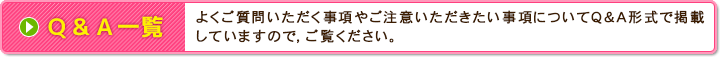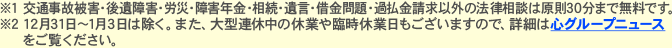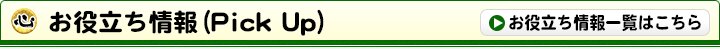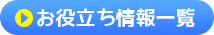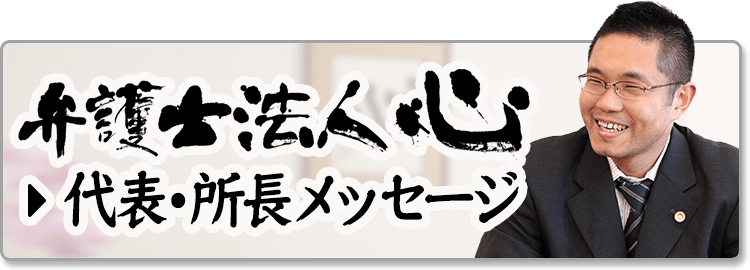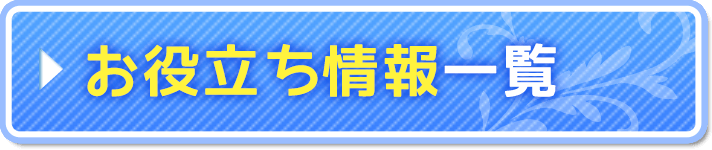遺言の作成をお考えの方へ

1 遺言を作成する際は弁護士にご相談ください
遺言の書き方には決められたルールがあり、そのルールに従っていないと、無効となってしまうおそれがあります。
また、遺言の内容があいまいであったりすると、かえって相続人同士の揉め事の原因となってしまう場合もあります。
相続人が揉めないように作成した遺言が、揉め事の火種となってしまっては本末転倒です。
そこで、書き方のルールや作成にあたってのアドバイス等を受けるためにも、遺言を作成する際は、相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
当法人には、遺言を得意とする弁護士がいますので、まず一度ご相談ください。
2 遺言を作成するメリット
自分の死後、遺産について家族同士で争ってほしくないというお気持ちから、遺言を作成しようとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。
遺言を作成しておけば、相続人同士で財産の分け方について決める必要がなくなるため、その分争いになることを避けられる可能性があります。
また、相続人の方にとっても、相続手続きをスムーズに進められるというメリットがあります。
相続手続きの中には、期限が設けられているものもあるため、いかに一連の手続きをスムーズに進められるかは重要となってきます。
他にも遺言を作成しておくメリットとして、遺産の分け方についてご自分の意思を反映できること、相続人以外の人に財産を残すことができること等が挙げられます。
3 どのような遺言を作成するのがよいか迷ったら弁護士へ
一言で遺言といってもいくつか種類があり、よく作成されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれにメリットやデメリットがありますので、ご自分の状況等に合わせてお選びになるのがよいかと思います。
そうはいっても、どういったメリットやデメリットが考えられるのか、どちらを選ぶとよいか等、自分自身で調べてみてもよく分からないということもあるのではないでしょうか。
また、自分で作成してみたものの、形式的に有効な遺言になっているか、内容に問題はないか等、不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。
遺言の作成や、作成した遺言書については、弁護士が相談にのらせていただくことができます。
4 遺言を得意とする弁護士が対応
当法人には、遺言など相続問題に関するご相談を集中して扱っている弁護士がいます。
まずは相続についてどのようなご意向があるかをお伺いし、遺言によって、誰に相続財産を引き継ぐのかを定めることで、どのような法律問題が起こるおそれがあるのかを十分に検討してまいります。
また、遺言を作成する際は、争いの火種とならないような内容面を考えることはもちろん、財産を相続するとかかる税金の面も考慮することで、より良い内容の遺言を作成できるよう、しっかりと対応させていただきます。
ご自分で作成した遺言の見直しについても、ご相談を承ります。
5 遺言について当法人に相談する際の流れ
遺言書を作成する際は、誰にどのような財産をどのぐらい引き継ぐのかを決めて、それを遺言に記載していくことになります。
残された相続人のことや、相続人同士の関係など、様々なことを考えながら内容を決めていくことになりますので、相談の限られた時間の中で一から検討するのは容易ではありません。
そのため、弁護士に相談する前に、あらかじめ大まかな方針を整理しておいていただけると、スムーズに相談できるかと思います。
弁護士は、相談者の方がどのような内容の遺言を作成したいとお考えなのかをお伺いさせていただき、内容に関するアドバイス等、よりよい遺言作成に向けて、対応させていただきます。
また、実際に遺言作成を弁護士に依頼した場合の費用等につきましても、ご相談の際にご説明させていただきます。
ご契約内容にご納得いただいた上で、弁護士に依頼するという流れになっております。
どなたにも気軽にご利用いただけるように、遺言の相談を原則無料とさせていただいているほか、横浜駅近くに事務所を設け、ご相談にお越しいただきやすい環境を整えています。
横浜で遺言の作成をお考えの方は当法人までご連絡ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
治療費の16条請求について 遺言書の内容に納得できない場合の対応
-
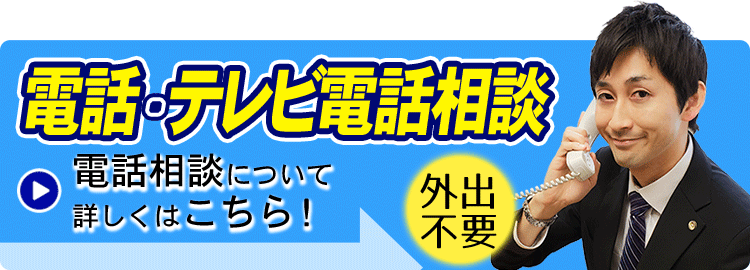

担当分野制を取り入れています
遺言のお悩みなら相続を得意とする弁護士が対応しますので、安心してご相談ください。
-
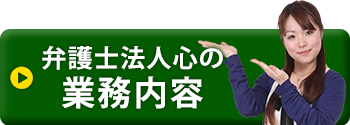
当法人の業務内容について
遺言のほかにも取り扱っている内容があります。詳細はこちらでご確認いただけます。
相談にもお越しいただきやすい立地です
所在地や地図などはこちらからご確認いただけます。横浜駅近くにも事務所があるため、相談にお越しいただく際もアクセスの良い立地です。
上手な遺言の利用方法
1 遺言書を作成する目的の明確化
遺言書を作成する際に最も重要なのは、何のために遺言書を作成するかを明確にすることです。
目的を明確にしているかどうかで、うまく遺言を利用して相続対策できるかが異なってきます。
今回は、目的との関係で上手な遺言の利用方法を紹介させていただきます。
2 特定の相続人に相続させないという目的

まず、遺言書の一番頻繁に使用される目的としては、特定の相続人に相続させたくないという点にあります。
遺言書は、特定の相続人又は第三者に対して財産を相続又は遺贈させることができるという効果を持っています。
裏返せば、相続させたくない人には財産を一切渡さないようにすることができるのです。
そのため、遺言書は特定の相続人に相続させないようにする方法として頻繁に利用されます。
ここで、上手な遺言書の利用方法として、兄弟姉妹が相続人となる場合に、遺言書を活用することで、特定の相続人に相続をさせず、一切の財産を渡さないということができます。
兄弟姉妹以外が相続人である場合は遺留分が発生するため、財産を一切もらえない相続人が遺留分を請求してくる可能性があります。
しかし、兄弟姉妹については、遺留分が認められていないため、遺言書で遺産分割方法の指定をすることで、本当に相続させたくない相続人に一切財産を渡たさないことが可能です。
3 親族がいない場合に第三者に財産を渡す場合
自身の財産を残したいが、死亡後に寄付をしたい場合や、相続人に対して諸事情から遺言書を作成したことを伝えたくない場合等については、遺言執行者の指定と法務局の通知制度を併用することで、自身が亡くなった後に安心して財産を相続させることができます。
法務局には、自筆証書遺言書を預けておくことで、指定した第三者に対して自身の死亡を通知することができます。
他方、公正証書遺言ではこのような制度がないため、遺言執行者が遺言者の死亡に気づかず、遺言の執行ができないという事態が想定されます。
そのため、このようなリスクを回避する目的で、公正証書遺言で信用性の高い遺言書を作成し、かつ自筆証書遺言を法務局に預けて遺言執行者を通知人に指定しておくことで、遺言の確実な執行を担保することができるようになります。
このような遺言制度の使い方も想定して、遺言書を作成するとよいかと思います。