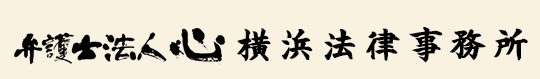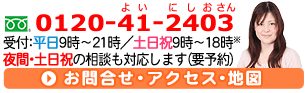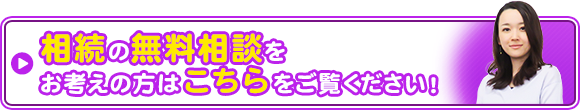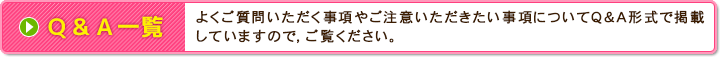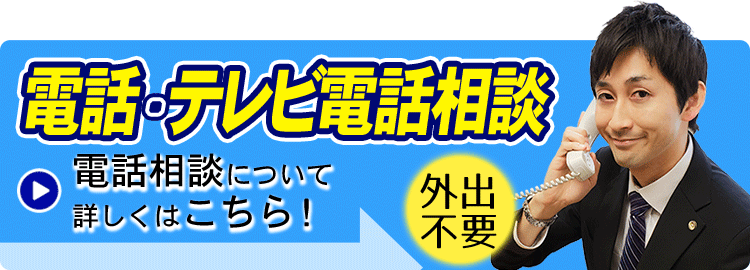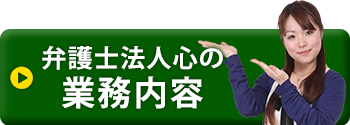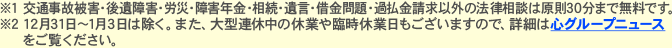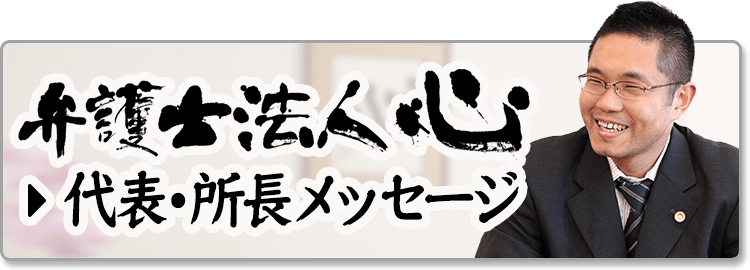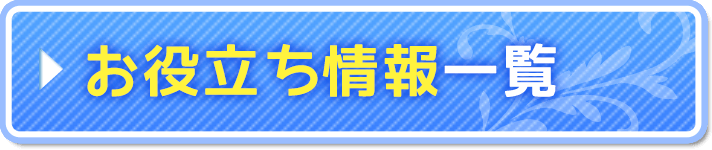相続登記について弁護士に相談が必要なケース
1 相続登記の義務化と相談先
令和6年4月1日以降、相続登記が相続人の義務となりました。
一定の期間内に相続登記を行わないと過料が課されてしまいますので、まずは期限に間に合うよう、手続きを行わなければなりません。
相続登記は、必要な書類を集めて、不動産の所在地を管轄する法務局で申請を行います。
ですが、慣れていない方にとっては、どのように手続きを進めるのか、必要な書類は何かが分からないこともあるかと思います。
そのような場合、どこに相談すべきか迷われることもあると思いますが、実は弁護士も登記に関する事務を行うこともできます。
以下では、相続登記について弁護士に相談が必要なケースをご紹介していきます。
2 相続した不動産を売却したい場合
相続した不動産を売却しようとする場合、亡くなられた方の名義のままでは売却はできません。
そのため、まずは相続人が取得した旨の相続登記を行う必要があります。
相続人の共有名義にするという相続登記をした場合、売却代金をその割合どおりに分配することになります。
他方、遺産分割協議書の記載方法によっては、便宜上単独名義で登記をして、相続人同士で売却代金を分配することもできます。
この点については、遺産分割協議書にどのように記載するかによって、譲渡所得税の課税関係でリスクが発生する可能性があります。
そのため、不動産の売却を前提とした相続登記については、弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、弁護士であれば、遺産分割協議書の作成も行うことができるため、上記のリスクを回避できるような協議書を作成してもらい、そのまま相続登記も依頼するということが可能です。
3 相続をしたくない不動産がある場合
一般的に価値のある宅地については、登記せずに放置されるケースはあまりありません。
難しいのは、「負の不動産」などと呼ばれる、相続をしたくないとされる不動産の登記についてです。
これら負の不動産については、不動産の放棄の制度を検討することになります。
参考リンク:法務省・相続土地国庫帰属制度について
なお、この不動産の放棄の制度についても、一定の管理費の支払いが必要となります。
この制度を利用する場合には、相続登記は不要です。
相続登記の費用や固定資産税の費用等と、不動産放棄のコストを比べて、どちらの方法にするのかを検討することになるかと思いますので、相続に詳しい弁護士にご相談ください。