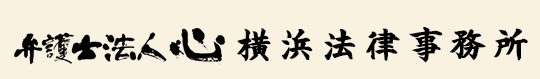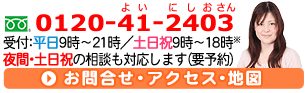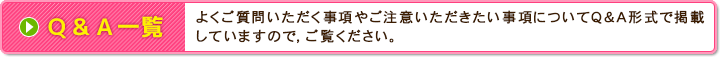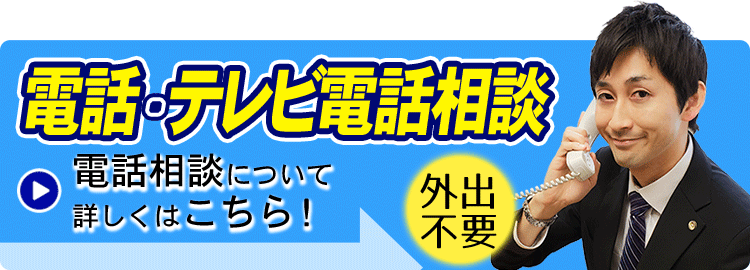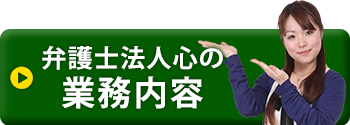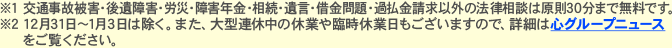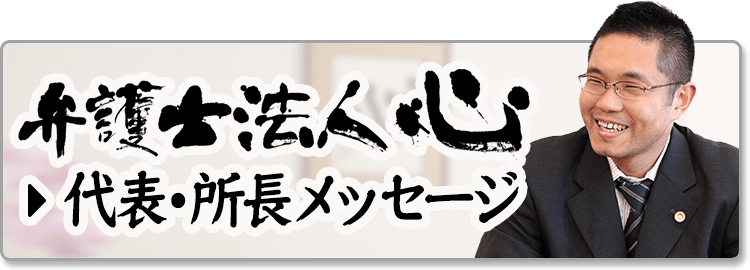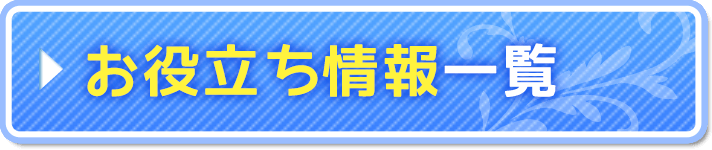遺産分割で調停・審判に至るまでの流れ
1 遺産分割の流れ
相続が開始したとき、遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容通りに遺産を分けます。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議による解決が困難な場合、調停・審判という、裁判所を通した手続きによって遺産の分け方を決めることになります。
以降でそれぞれ詳しく説明いたします。
2 遺産分割協議
遺産の分け方について、相続人全員で行う話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議を行い、協議に基づく内容で遺産を分けることができます。
また、遺言書から漏れている遺産があるような場合には、その遺産については別途遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するかを話し合うほか、特別受益や寄与分の主張がある場合には、それを考慮したうえでの遺産分割方法を提案することができます。
遺産分割協議において、相続人全員で合意ができない場合には、遺産分割調停・審判へと進みます。
3 遺産分割調停
他の相続人から提案された遺産分割方法に納得がいかないなど、任意での遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合や、相手方が協議に応じようとしない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停は、調停委員が間に入って当事者間での話し合いでの合意を目指す手続きです。
原則、調停員が当事者から交互に話を聞き、双方の希望や論点を整理したうえで、合意による解決に向けて手続きを進めていきます。
この調停手続きでも合意をすることができない場合には、遺産分割審判に移行することになります。
4 遺産分割審判
遺産分割審判では、期日が指定され、その期日に当事者同士が対面して手続きが進むことになります。
調停はあくまでも話し合いの場でしたが、審判は、裁判所が事実関係を踏まえて、法的な判断をする場になります。
審判は、複数回の期日が設けられることが通常で、その期間は、数か月から1年程度かかることもあります。
双方の主張と証拠の提出が尽くされると、裁判官が遺産分割方法や内容についての審判をすることになります。
審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間が経過すると審判内容が確定します。
一方で、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内の間であれば不服の申立てをすることができます。
これを即時抗告といいます。
即時抗告をすると、高等裁判所にて審理を行うことになります。
相続人に未成年の子どもがいる場合の遺産分割 不動産しかない場合、遺産分割はどのようにしたらよいのか